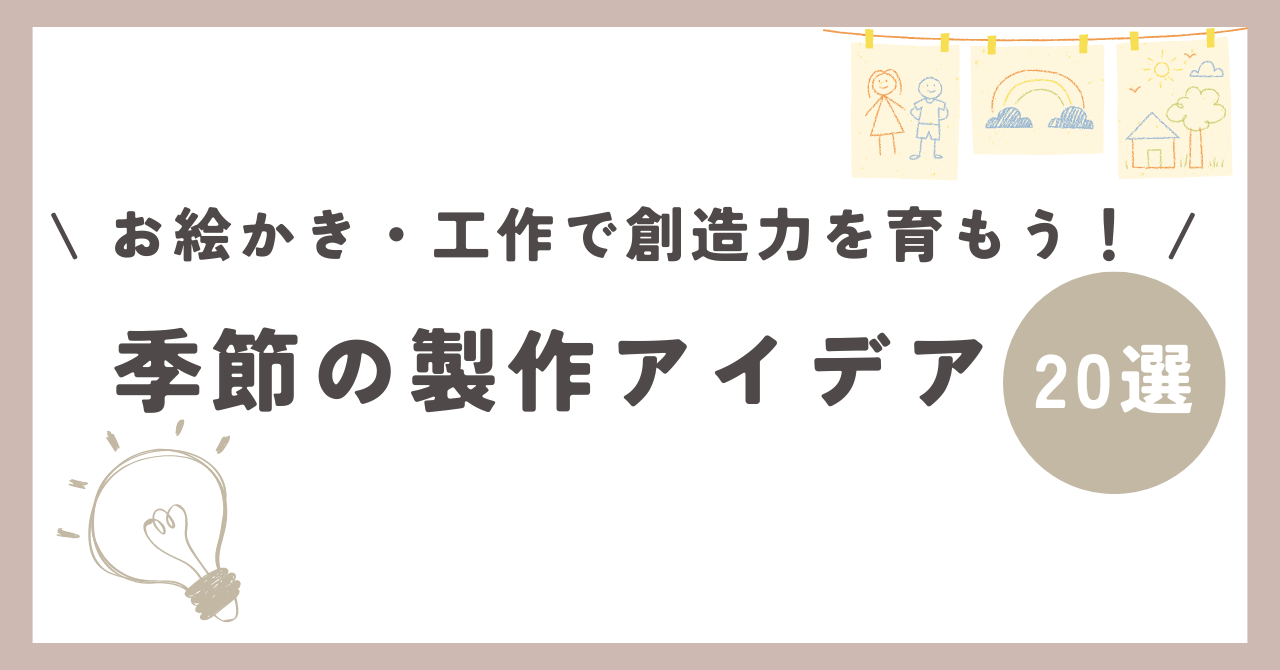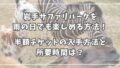今回は、お絵かきや工作を通して子供の創造力を伸ばす方法について、たっぷりとお話ししたいと思います。
1. お絵かき・工作の発達段階と見守り方

子供のお絵かきや工作は、成長に合わせて少しずつ変化していきます。
それぞれの発達段階の特徴を理解し、適切に見守ることが大切です。
- 1歳頃:なぐり描きの時期。クレヨンを握る、紙に点をつけるなど、描く動作を楽しむ。
- 2歳頃:円を描けるようになる。自分の感覚を表現しようとする。
- 3歳頃:顔や家など、具体的なものを描き始める。色の選択にも興味を示す。
- 4歳頃:絵に物語性が出てくる。友達と一緒に製作を楽しむ。
- 5歳頃:写実的な表現が増える。集中力も高まり、細かい作業ができるように。
子供の表現をほめたり、一緒に作品について話したりしながら、創造する楽しさを味わえるよう働きかけましょう。
ママが一緒に楽しむ姿勢を見せることも大切ですよ。
2. 色・形・模様の基礎知識
色や形、模様の基礎を学ぶことは、子供の感性を豊かにするために重要です。
日常生活の中で、色の名前を伝えたり、形や模様に気づかせたりする機会を作りましょう。
- 色の三属性(色相・明度・彩度)を知る
- 色の分類(有彩色・無彩色、暖色・寒色など)を理解する
- 形の種類(円・三角・四角など)や特徴に気づく
- 身の回りの模様(ストライプ・ドット・チェックなど)を探す
絵本や美術館などで、色や形、模様の多様性に触れる経験も大切。
子供の興味関心に合わせて、楽しく学べる環境を整えてあげたいですね。
3. 季節や行事に合わせた製作アイデア20選
季節の移り変わりや年中行事は、子供の製作意欲を高めるのにぴったり。
身近な素材を使って、季節感あふれる作品作りを楽しみましょう。
春
1. お花紙で作る桜の壁面飾り
- 桜の花びらの形に切った色とりどりのお花紙を、子供に自由に丸めたり折ったりしてもらいます。
- 画用紙に桜の木の幹と枝を描き、そこに花びらを貼り付けていきます。
- たくさんの花びらを重ねて貼ると、立体的で豪華な桜の壁面飾りの完成です。
2. こいのぼり製作
- 画用紙に鯉のぼりの形を描いて切り取ります。
- 色画用紙や折り紙を切ってウロコに見立て、鯉のぼりに貼り付けます。
- 口の部分に割り箸などを貼り付け、糸を通せば、こいのぼりのできあがり。
- 子供の顔写真を貼ると、世界に一つだけのこいのぼりになりますよ。
3. 春の野菜スタンプアート
- ジャガイモやタケノコ、キャベツなど、春野菜を半分に切ります。
- 切り口にアクリル絵の具をつけて、画用紙に押し付けます。
- 野菜の形や模様が印刷されて、不思議な春の絵ができあがります。
4. 春の草花を描こう
- 春に咲く身近な草花(タンポポ、レンゲソウ、チューリップなど)を道で見つけたり、写真を見せたりします。
- クレヨンやパステル、絵の具など、好きな画材を使って、春の草花を思い思いに表現します。
5. 春のピクニック風景のコラージュ
- 画用紙の上に、色画用紙や包装紙を切ったり破ったりして貼り、ピクニックの情景を表現します。
- 空や芝生、お弁当やレジャーシートなど、春の屋外の雰囲気を思い思いに表現できます。
夏
6. 貝殻を使ったフォトフレーム
- 画用紙に写真を貼るフォトフレームの土台を作ります。
- 子供が拾ってきた貝殻を、ボンドで周りに貼り付けて飾り付けます。
- 夏の思い出の写真を入れれば、世界に一つの宝物のできあがりです。
7. 風鈴作り
- ペットボトルを底の方を切り取り、キラキラしたシールを内側に貼ります。
- 口の部分にビーズのついた紐を通して、窓際などに吊るします。
- 風に揺れるたびに、手作りの音が響く風鈴になります。
8. サンゴ礁の水族館ジオラマ
- 空き箱の中に、色画用紙で海の背景を作ります。
- サンゴはスポンジや毛糸を使って表現し、魚は折り紙で作って泳がせます。
- 南国の海の中をイメージした、涼し気なジオラマができあがります。
9. アイスクリーム屋さんごっこ
- 空き箱で作ったアイスクリーム屋さんの店舗と、色画用紙で作ったアイスクリームのコーンを用意します。
- 中にはスポンジや色紙をちぎって詰め、アイスクリームに見立てます。
- 屋台で売り子になったり、お客さんになったりして、ごっこ遊びが楽しめます。
10. 夏祭りの思い出絵日記
- 夏祭りに行ったり、行った時の写真を見せて、楽しかった思い出を語り合います。
- 画用紙に、金魚すくいや輪投げ、かき氷など、夏祭りの様子を絵と文で表現します。
- みんなの思い出が詰まった夏祭りの絵日記が完成します。
秋
11. 落ち葉や木の実を使ったコラージュ
- 子供と一緒に、公園などで綺麗な落ち葉や木の実を拾ってきます。
- 画用紙に、拾ってきた自然の素材を貼り付けて、秋の情景を表現します。
- ドングリ坊やや栗のイガイガ鬼など、想像上の生き物を作るのも面白いですね。
※ドングリは中に虫がいることもあるので、煮沸や冷凍であらかじめ駆除しておくことをおすすめします!
参考:どんぐりに潜む危険を対処!煮沸や冷凍で「虫を駆除」
12. ハロウィンの仮装グッズ作り
- ハロウィンの仮装に使う帽子やお面、マントなどを画用紙で作ります。
- 魔女の帽子は画用紙を三角に折って、クモの巣模様を描きます。
- お化けのお面は、画用紙に顔を描いて、目の部分を切り抜きます。
13. 秋の味覚狩りの思い出絵
- りんご狩りやぶどう狩りなど、秋の味覚狩りに行ったり、行った時の写真を見せます。
- 画用紙に、味覚狩りの様子を絵に描きます。
- りんごの木やぶどうの房、美味しそうに食べている自分の姿など、楽しい思い出が蘇ります。
14. どんぐりゴマ作り
- 子供と一緒に拾ってきたドングリに、つまようじを刺してゴマを作ります。
- 画用紙に地面を書いて、その上でコマ回しを楽しみます。
※どんぐりの虫の駆除については、「11.落ち葉や木の実を使ったコラージュ」をご参照ください。
15. 七五三の千歳飴袋作り
- 七五三のお祝いに欠かせない千歳飴の袋を、画用紙で手作りします。
- 袋の表面に、子供の成長を祝う言葉や絵を描きます。
- 中に千歳飴(大きすぎる場合は、子どもが食べられるサイズのペロペロキャンディーなど)を入れれば、オリジナルのお祝いの品のできあがりです。
冬
16. 雪だるまやサンタクロースの製作
- 綿や色画用紙を使って、雪だるまやサンタクロースを作ります。
- 雪だるまは綿を丸めて重ね、目や口、マフラーを色画用紙で作って貼ります。
- サンタクロースは、赤い画用紙で体を、綿で髭を表現します。
17. クリスマスリース作り
- 画用紙を輪っかの形に切り、それを土台にしてリースを作ります。
- 松ぼっくりやドングリ、リボンなどを飾り付けます。
18. お正月の門松飾り
- 画用紙で門松の土台を作り、色画用紙で竹や松の葉を表現します。
- ちょうちんや注連縄も色画用紙で作って飾り付けます。
19. 冬の星空ランプシェード
- 画用紙で円錐形のランプシェードを作ります。
- シェードに星の形を切り抜いたり、シールを貼ったりして飾り付けます。
- 中に電球を入れれば、幻想的な冬の星空が浮かび上がります。
20. 節分の鬼のお面作り
- 画用紙で鬼のお面の土台を作ります。
- 角や歯、髭など、鬼の特徴的なパーツを色画用紙で作って貼り付けます。
親子で一緒に製作する時間を設けることで、コミュニケーションを深めながら、子供の創造性を育むことができます。
4. リサイクル素材を使った工作
空き箱や牛乳パック、ペットボトルなど、身近にあるリサイクル素材は、工作に最適。
廃材を使って作ることで、物を大切にする心も育みます。
- 牛乳パックで作る動物の貯金箱
- ペットボトルのキャップで作るコマ
- 段ボール箱で作る子供用の家具
- 新聞紙で作るエコバッグ
- 空き瓶のスノードーム
- 空き缶の風鈴
- 包装紙で作るブックカバー
- 古着を使ったぬいぐるみ
リサイクル工作は、材料集めから始まる楽しみがあります。
子供と一緒に素材探しをしながら、アイデアを膨らませていきましょう。
5. 美術館・博物館の活用法
美術館や博物館は、子供の創造力を刺激する場所。
本物の芸術作品に触れることで、表現の多様性を知り、感性を磨くことができます。
- 企画展や常設展示を親子で鑑賞する
- ワークショップやイベントに参加する
- ミュージアムショップでお気に入りのグッズを見つける
- 美術館の建物や庭園の雰囲気を味わう
- 作品から感じたことを話し合う
- 気に入った作品を真似して描いてみる
- 博物館の展示から歴史や文化を学ぶ
- 美術館巡りの旅行計画を立てる
作品を見るだけでなく、感じたことを話し合ったり、描いたりすることで、美術館での体験をより深めることができるでしょう。
お絵かきや工作は、子供の創造力を育む素晴らしい活動です。
発達に合わせた見守りを心がけながら、季節やリサイクル素材を取り入れた製作を楽しんだり、美術館などで芸術に触れる機会を作ったりして、子供の可能性を広げていきましょう。
ママも一緒に楽しみながら、子供の創造力を育てていきたいですね。