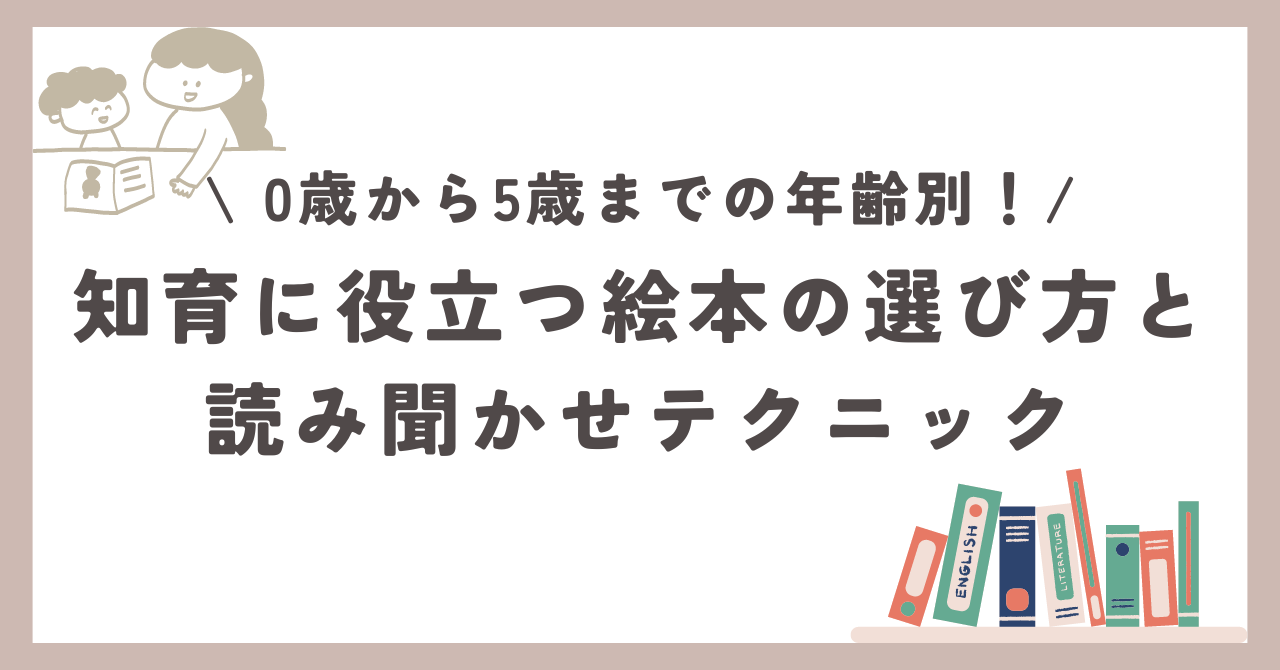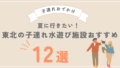今回は、0歳から5歳までのお子さんの発達段階に合わせた、知育に役立つ絵本をご紹介します。
読み聞かせテクニックについても詳しくお話します。
0歳におすすめの絵本
0歳の赤ちゃんには、シンプルな絵柄と言葉の繰り返しがある絵本がおすすめです。
この時期の子供は、絵を見て言葉と結びつける力を育んでいます。
「いないいないばあ」シリーズ(松谷みよ子・作、瀬川康男・絵)
日本の絵本ではじめて!『いないいないばあ』が700万部を突破しました。1967年の刊行から約半世紀。「あかちゃんがほんとうに笑うんです」刊行当時の帯のキャッチコピーのとおり、あかちゃんの毎日に笑顔を届けてきました。https://t.co/ItiYVywdPp pic.twitter.com/G01aKMEHag
— 童心社 (@doshinsha) November 23, 2020
このシリーズは、50年以上も愛され続けているベストセラーの言葉遊び絵本です。
「いないいない…」と声をかけてページをめくると、「ばあ」とかわいいキャラクターが現れる仕掛けになっています。
シンプルな言葉の繰り返しと、温かみのある優しいタッチの絵が、赤ちゃんの興味を引き付けます。
親子のふれあいを楽しみながら、言葉と絵を結びつける力を育むのに最適な一冊です。
「だるまさんが」シリーズ(かがくいひろし・作)
シンプルな絵と、リズミカルな言葉の繰り返しが特徴の絵本です。
「だるまさんが…」に続いて、転んだり縮んだり、ユーモラスに動くだるまさんが赤ちゃんの興味を引き付けます。
絵本に合わせて体を動かすことで、赤ちゃんの身体能力の発達も促せるでしょう。
誰が読んでも子どもが笑ってくれやすい名作です。
「ぱかっ」(森あさ子・作)
「ぱかっ」と、ページをめくるたびに次々と何かが飛び出してきます。
「たまごさん たまごさん」と呼びかけてページをめくると、卵からひよこが顔を出す、といった具合に、赤ちゃんにも分かりやすい言葉とシンプルな絵で構成されています。
カラフルで楽しい絵と、言葉の繰り返しが、赤ちゃんの興味を引き付けます。
ページをめくる動作を通して指先の発達も促せる、赤ちゃんの成長に寄り添える一冊です。
1歳におすすめの絵本
1歳頃になると、ストーリー性のある絵本を楽しめるようになります。
想像力を育み、感情移入しながら物語を楽しめるようになります。
「はらぺこあおむし」(エリック・カール・作)
鮮やかな色彩とシンプルなストーリーが魅力の絵本です。
おなかをすかせた青虫が、果物や食べ物をたくさん食べて、最後には美しい蝶になるまでの成長物語が描かれています。
穴が開いたページや、ユニークな絵の具の使い方など、子どもの視覚を刺激する仕掛けが満載です。
数の概念も自然と学べる内容になっており、子どもの知的好奇心を育てるのにぴったりです。
「きんぎょがにげた」(五味太郎・作)
鮮やかな色彩で描かれた、きんぎょを探す絵探し絵本です。
絵本の中できんぎょを見つけ出す遊びを通して、集中力や観察力を養うことができます。
絵本の中には、きんぎょ以外にも、草や木、小動物など、たくさんの自然の要素が描き込まれています。
これらを指差しながら一緒に探すことで、子どもの好奇心を刺激し、言葉の習得にもつなげられます。
絵本の世界を通して、子どもの探究心を育んでいきましょう。
「おべんとうバス」シリーズ(真珠まりこ・作、うちのますみ・絵)
乗り物が好きな子ども、食べ物が好きな子どもにおすすめの絵本です。
お弁当の食べ物たちが、呼ばれたら返事をしてバスに乗り込んでいく内容です。
かわいい食べ物たちと一緒に元気よく「はーい!」と返事をする練習をしたり、楽しみながらお弁当の具材の名前を覚える練習ができます。
2歳におすすめの絵本
2歳頃になると、言葉の意味を理解し、物語を通して考える力を育みます。
言葉遊びやユーモアのある絵本がおすすめです。
「もこ もこもこ」(谷川俊太郎・作、元永定正・絵)
地面から謎の物体が「もこ」と飛び出し、それがどんどん成長して、最後には…!?
謎がいっぱいの絵本ですが、声に出してみると音のリズムの良さが秀逸。
ユーモラスな絵と、想像力をかきたてる言葉のマジックに、子どもは引き込まれることでしょう。
ぜったいに おしちゃダメ?(ビル・コッター・作)
押しちゃダメ、と言われると押したくなるのが人の性ですよね。
絶対に押したらいけないボタンを「押しちゃおうか?」と誘惑してくるキャラクターにつられて、絵本の中のボタンを押したり、いやいやダメだと我慢したり。
子どもの好奇心がくすぐられて、何度も繰り返し読みたがる一冊です。
3歳におすすめの絵本
3歳頃になると、お話の内容を理解し、登場人物の気持ちを想像できるようになります。
物語性のある絵本や、知的好奇心を刺激する絵本がおすすめです。
「ぐりとぐら」シリーズ(なかがわりえこ・作、おおむらゆりこ・絵)
優しい色合いの絵と、ほのぼのとした雰囲気で、長く愛されている人気作です。
親世代にも、昔好きだったなぁ~という人が多いのでは。
シンプルな言葉で綴られたストーリーは、子どもの言語発達を促すのにも向いています。
絵本の中で繰り広げられる、ぐりとぐらの優しい世界観に触れることで、子どもの情緒面の成長も期待できます。
「ノンタン」シリーズ(キヨノ サチコ・作)
ノンタンシリーズも、発売以来長く愛されている名著の一つ。
主人公のノンタンは、元気いっぱいの子猫で、毎日が楽しい冒険の連続です。
シンプルでわかりやすいストーリーと、愛らしいキャラクターが魅力です。
絵本の中では、ノンタンが身近な場所で遊ぶ様子が描かれています。公園や砂場など、お子様にとって親しみやすい舞台設定になっているので、ノンタンの世界に入り込みやすいでしょう。
「100かいだてのいえ」(いわい としお・作)
この絵本は、タイトル通り、100階建ての家の中を探検するストーリーです。
絵本のページを開くたびに、いろんな動物が住む家の中のさまざまな部屋が現れます。
細部まで丁寧に描き込まれたイラストを眺めながら、想像力を膨らませることができますよ。
絵本の中には、数字の勉強にもなるような仕掛けが盛り込まれています。
子どもの観察力や集中力を養いながら、楽しく数の概念に触れることができる一冊です。
4歳におすすめの絵本
4歳頃になると、言葉の意味をより深く理解し、物語の背景にある世界観にも興味を持ち始めます。
想像力を刺激する絵本や、言葉遊びを楽しめる絵本がおすすめです。
「からすのパンやさん」(かこ さとし・作)
この絵本は、からすのパン屋さんを舞台に、ユニークなパンの数々が登場する楽しいお話です。
細部まで丁寧に描き込まれた様々なパンのイラストは、ユーモアたっぷりながらとてもおいしそうでもあります。
ページをめくるたびに現れる、一風変わった形のパンに、子どもたちはとりこになるはず。
想像力豊かなストーリーを通して、子どもの創造力を育むのにぴったりの一冊です。
「こんとあき」(林 明子・作)
ぬいぐるみの「こん」と女の子の「あきちゃん」がおばあちゃんの家へ向かう物語です。
こんとあきちゃんの心温まる絆は、子どもの情緒面の発達を助け、大人にとっても心にくるものがあります。
深い愛情を根底に感じる優しい絵本です。
5歳におすすめの絵本
5歳頃になると、物語の背景にある世界観を理解し、登場人物の心情を想像できるようになります。感情移入しやすい絵本や、知的好奇心を刺激する絵本がおすすめです。
「スイミー」(レオ・レオニ作、谷川俊太郎・訳)
小さな黒い魚のスイミーが仲間と出会い、知恵と勇気で大きな困難に立ち向かう物語です。
スイミーは最初、兄弟を失って一人ぼっちでしたが、新しい仲間と出会い、みんなで力を合わせることの大切さを学びます。
鮮やかな色彩と美しい絵が印象的で、子どもたちの想像力を刺激します。
勇気と友情、そして協力することの素晴らしさを教えてくれる、心温まる作品です。
「ひみつのカレーライス」(井上荒野・作、田中清代・絵)
カレーライスを食べていると、口の中から種が出てきた。
それを埋めると、やがて…?
作中に出てくるカレーがなんともおいしそうで、読んだらカレーが食べたくなること間違いなし!
直木賞作家、井上荒野さんの絵本デビュ―作です。
「ねずみくんのチョッキ」シリーズ(なかえよしを・作、上野紀子・絵)
出版されて50年を迎えるロングセラー絵本。
おかあさんが編んでくれた赤いチョッキをねずみくんが嬉しそうに着ていたら、次々と動物たちが現れて「ちょっと着せてよ」と…。
大切なチョッキはどうなってしまうのでしょうか。
イラストはシンプルながら、表情豊かなキャラクターたちが魅力的です。
絵本の読み聞かせテクニック
絵本の読み聞かせは、子供の言語能力や想像力を育む大切な時間です。
以下のような点を意識してみましょう。
- ゆっくりとした語り口で、表情豊かに読む
- 絵を指差しながら、内容に関する問いかけをする
- 子供の反応を見ながら、ペースを調整する
- 読み聞かせ後は、感想を聞いたり、内容について話し合う
絵本を使った知育あそびのアイデア
絵本は、知育あそびのヒントにもなります。
絵本の内容を発展させた遊びを取り入れることで、子供の学びをさらに深めることができます。
例えば、絵本に出てくる動物や乗り物の実物や写真などを見る。
動物園に行ったり、写真や動画を見てみたりして、実際の大きさや迫力を知ると、より一層印象に残りやすくなります。
絵本に出てくる料理を実際に作ってみるのも楽しいアイディア。
「ぐりとぐらのパンケーキ」を作ったりすると、楽しい思い出とともに記憶に残ります。
絵本に出てくる料理のレシピ集も発売されていますよ。
絵本は、子供の成長に欠かせない存在です。
発達段階に合わせて絵本を選び、読み聞かせのテクニックを磨くことで、子供の可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。
絵本を通して、親子の絆を深めながら、楽しく知育に取り組んでいきましょう。